退職をいつまでに伝えるべき?法律と実務のポイントを徹底解説
退職を考える際「いつまでに会社に伝えればいいのか」や「法律ではどう定められているのか」と悩む人は少なくありません。退職のタイミングや伝え方には、法律や就業規則に基づくルールが存在し、これを理解しておくことでスムーズな退職が実現します。
本記事では、退職の申し出時期に関する法律、就業規則との関係、実際の退職手続きの流れ、そして円満退職のためのポイントを詳しく解説します。「退職 いつまでに伝える 法律」で検索するあなたの疑問をすべて解決する内容をお届けします。
退職の申し出時期を定める法律とは?
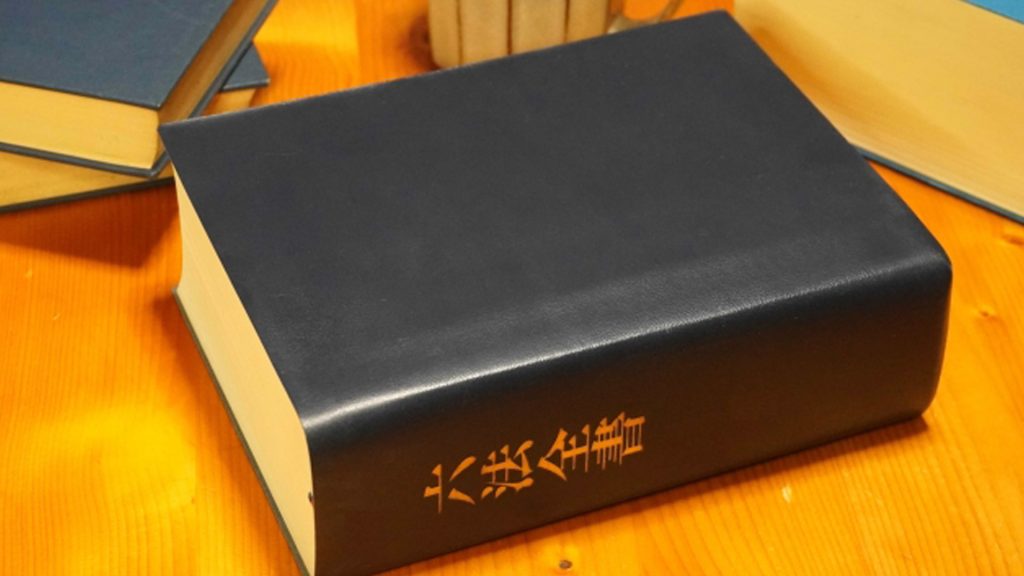
民法627条が基本ルール
日本では、退職の申し出時期に関する基本的なルールが民法第627条に定められています。この条文によると、正社員(期間の定めのない労働契約)の場合、退職の意思を伝えた日から2週間後に退職が成立します。つまり、法律上は「2週間前に伝えれば退職できる」というのが原則です。
具体的には、以下のように定められています。
- 労働者が退職の意思を表明した場合、2週間後に労働契約が終了。
- 特別な事情がない限り、会社の承認は不要。
このルールは、労働者が自由に退職する権利を保障するためのもので、会社側が一方的に退職を拒否することはできません。ただし、実際にはこの「2週間」という期間だけで退職するのはまれで、会社の就業規則や業務の引き継ぎを考慮する必要があります。
契約社員やパートの場合
契約社員やパートなど、期間の定めのある労働契約の場合、原則として契約期間満了まで働く必要があります。
ただし、やむを得ない理由(例:健康上の理由、家庭の事情)があれば、契約期間中でも退職が認められる場合があります(民法628条)。この場合も、退職の申し出はできるだけ早めに行うことが望ましいです。
就業規則による退職のルール
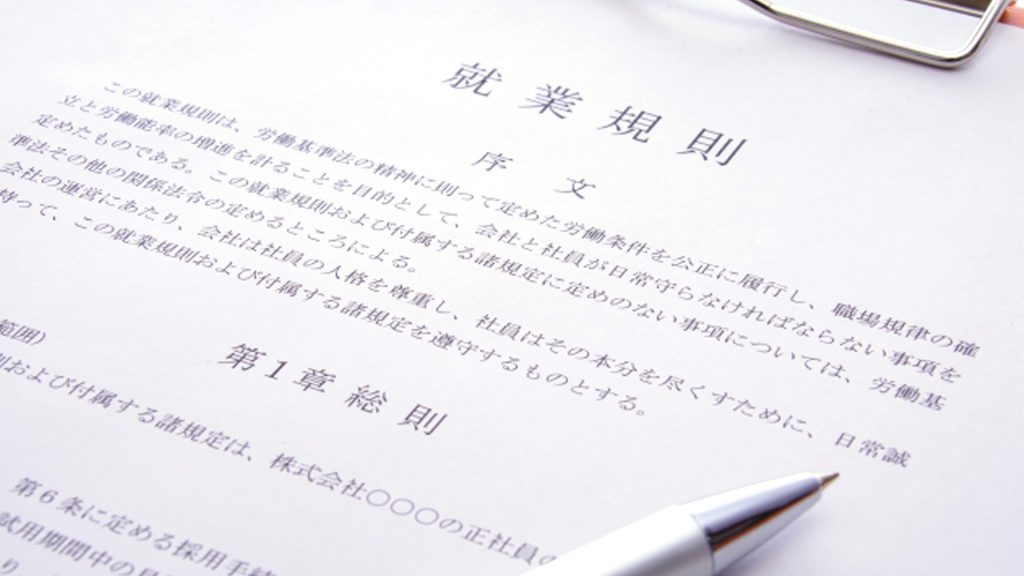
就業規則は法律より優先される?
多くの企業では、就業規則で退職の申し出時期を定めています。一般的には、「退職の1ヶ月前または2ヶ月前までに申し出ること」と記載されているケースが多いです。民法の「2週間」と比較すると、就業規則のルールの方が長期間を求める傾向にあります。
ただし、就業規則のルールが民法よりも厳しい場合、法的には民法の2週間ルールが優先されます。とはいえ、円満退職を目指すなら、就業規則に従って早めに伝えるのが現実的です。会社側も引き継ぎや後任の準備に時間を必要とするため、協力的な姿勢を見せることでトラブルを避けられます。
就業規則の確認方法
退職を考える際は、まず会社の就業規則を確認しましょう。就業規則は以下で入手可能です。
- 職場のイントラネットや社内ポータルサイト
- 人事部や総務部への問い合わせ
- 労働基準監督署(就業規則は提出義務があるため)
特に、退職の申し出時期、退職手続きの流れ、有給休暇の消化ルールなどをチェックしておくと安心です。
退職の申し出時期の目安

一般的な目安は1~2ヶ月前
法律では2週間前でも退職可能ですが、実際には1〜2ヶ月前に伝えるのが一般的です。以下のような理由から、早めの申し出が推奨されます。
- 業務の引き継ぎ:後任や同僚に業務内容を教える時間が必要。
- 会社のスケジュール:欠員補充や採用活動に時間がかかる。
- 人間関係の維持:急な退職は職場に迷惑をかける可能性があり、将来の関係に影響する。
特に、責任あるポジションや専門性の高い業務に従事している場合、引き継ぎに時間がかかるため、2ヶ月以上前に伝えるケースも珍しくありません。
繁忙期やプロジェクトのタイミングを考慮
退職のタイミングは、職場の状況も考慮しましょう。たとえば、以下のような時期は避けた方が無難です。
- 繁忙期(例:年末年始、決算期)
- 大きなプロジェクトの佳境
- 上司や同僚が休暇中の時期
こうしたタイミングで退職を申し出ると、職場に負担がかかり、円満退職が難しくなる可能性があります。
円満退職のための伝え方のコツ

直属の上司にまず相談
退職の意思を伝える際は、直属の上司に最初に相談するのがマナーです。同僚や人事部に先に話すと、情報が混乱したり、上司との信頼関係が損なわれたりするリスクがあります。以下の手順で進めましょう。
- 上司と1対1で話す時間を確保(面談やオンライン会議)
- 退職の意思と理由を簡潔に伝える
- 退職希望日(例:1ヶ月後、2ヶ月後)を提案
退職理由は前向きに
退職理由を聞かれた場合、ネガティブな内容(例:職場の不満、給与への不満)は避け、前向きな理由を伝えるのが賢明です。たとえば
- 新しいキャリアに挑戦したい
- スキルアップを目指して勉強に専念したい
- 家庭の事情で働き方を変えたい
こうした理由なら、上司も納得しやすく、引き止められるリスクも減ります。
退職届の提出
退職の意思が固まったら、正式に退職届を提出します。退職届には以下の項目を記載します。
- 提出日
- 退職希望日
- 自分の氏名と所属
- 簡単な退職理由(例:「一身上の都合により」)
退職届はA4用紙に手書きまたはパソコンで作成し、封筒に入れて上司または人事部に提出します。
有給休暇の消化と退職

有給休暇は法律で認められた権利
退職時には、残っている有給休暇を消化する権利があります(労働基準法第39条)。会社側が有給消化を拒否することはできません。ただし、消化のタイミングは業務の状況を考慮して調整するのが一般的です。
有給消化の伝え方
有給消化を希望する場合、退職の申し出時に以下のように伝えるとスムーズです
「退職前に残りの有給休暇を消化したいと考えています。どのタイミングが適切でしょうか?」や「引き継ぎを終えた後、有給を消化させていただければ幸いです。」など、こうした提案をすることで、会社側との調整がしやすくなります。
退職時の注意点とトラブル回避

引き止めへの対応
退職を申し出ると、会社から引き止められるケースがあります。引き止めに応じるかどうかは自由ですが、以下のように対応するとよいでしょう。
- 退職の意思が固いことを丁寧に伝える
- 引き止めの提案(例:給与アップ、異動)を検討しつつ、自分のキャリアプランを優先
退職を認めないと言われた場合
会社が「退職を認めない」と主張しても、民法627条に基づき、2週間後に退職は成立します。ただし、トラブルを避けるため、以下の対応を検討してください。
- 就業規則を確認し、ルールに従っていることを主張。
- 労働基準監督署や弁護士に相談。
- 退職届を内容証明郵便で送付(証拠として残る)。
退職後の手続き
退職後は、以下の手続きが必要です:
- 健康保険や年金の手続き(国民健康保険への切り替えなど)
- 失業保険の申請(ハローワーク)
- 離職票や源泉徴収票の受け取り
まとめ 退職は計画的に進めよう
法律的に退職はいつまでに伝えるのか?に関する疑問をまとめると、以下のポイントが重要です。
- 法律上は、退職の2週間前に申し出ればOK(民法627条)
- 就業規則では、1〜2ヶ月前の申し出が一般的
- 円満退職を目指すなら、早めの相談と引き継ぎの準備が不可欠
- 有給休暇の消化や退職後の手続きも忘れずに





















