退職金いくらもらえる?金額の目安や計算方法を徹底解説
退職金は、長年の勤続に対する企業からの感謝のしるしであり、退職後の生活を支える重要な資金です。しかし、「退職金はいくらもらえるのか」「どうやって計算されるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、退職金の金額の目安、計算方法、制度の種類、税金や受け取り方の注意点まで、わかりやすく解説します。退職金に関する不安を解消し、将来のライフプランに役立つ情報を提供します。
退職金とは?基本を押さえる
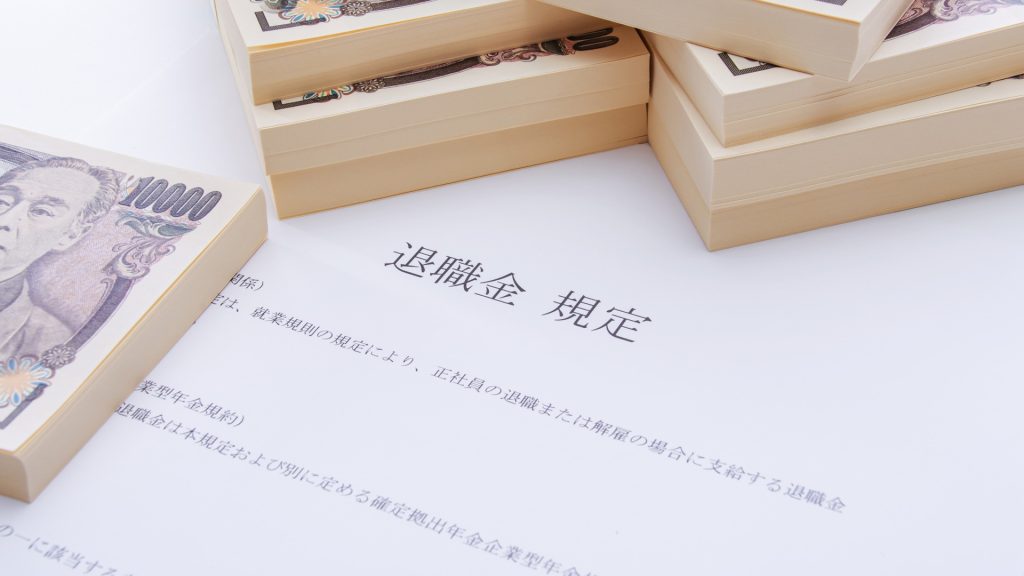
退職金とは、従業員が会社を退職する際に支払われる一時金や年金のことを指します。主に長期間勤務した社員への報奨や、退職後の生活支援を目的として支給されます。ただし、退職金制度は法律で義務付けられているわけではなく、企業によって制度の有無や内容が異なります。
厚生労働省の調査(2023年)によると、約80%の企業が何らかの退職金制度を導入しています。しかし、近年は退職金制度を見直す企業も増えており、従来の「退職一時金」だけでなく、「確定拠出年金(DC)」や「確定給付年金(DB)」を組み合わせた制度も一般的です。
退職金の種類
- 退職一時金:退職時に一括で支払われる金額。
- 企業年金:退職後に分割で支払われる年金形式。
- 確定拠出年金(DC):従業員が自分で運用し、退職時に受け取る。
- 確定給付年金(DB):企業が約束した金額を退職後に受け取る。
退職金の金額や形式は、企業の規模、業種、勤続年数、役職などによって大きく異なります。では、具体的に「退職金はいくらもらえる」のでしょうか?次で詳しく見ていきましょう。
退職金の金額の目安
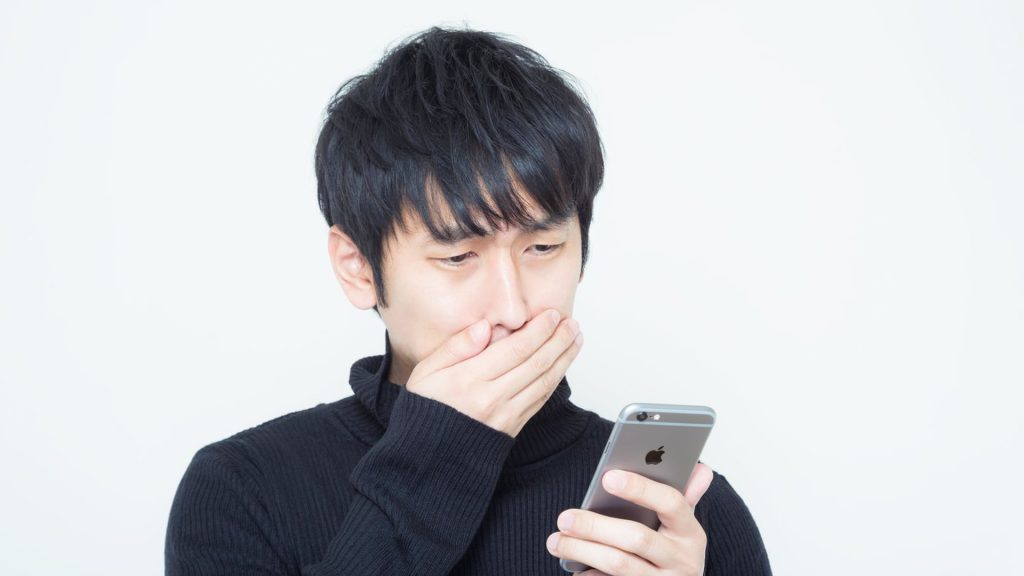
退職金の金額は、勤続年数や退職時の給与、企業の制度によって決まります。ここでは、一般的な目安を紹介します。
大企業の退職金
大企業(従業員1000人以上)の場合、退職金は比較的手厚い傾向があります。中央労働委員会の調査(2022年)によると、大学卒で勤続35年(60歳定年)の場合、退職金の平均額は約2000万円~2500万円です。ただし、役職や業績によって500万円以上の差が生じることもあります。
中小企業の退職金
中小企業(従業員100人未満)では、退職金の金額は大企業に比べて控えめです。同じく勤続35年の場合、平均額は約1000万円~1500万円程度とされています。中小企業では退職金制度自体がない場合もあるため、事前に就業規則を確認することが重要です。
公務員の退職金
国家公務員や地方公務員の退職金は、法律に基づいて計算されます。2023年のデータでは、勤続35年の国家公務員(行政職)の退職金は約2100万円~2300万円が目安です。ただし、近年は公務員の退職金も削減傾向にあり、以前ほど高額ではありません。
勤続年数別の目安
以下は、一般的な退職金の目安を勤続年数別にまとめたものです(大企業の場合、退職一時金のみ):
- 勤続10年:約300万円~500万円
- 勤続20年:約800万円~1200万円
- 勤続30年:約1500万円~2000万円
- 勤続40年:約2000万円~3000万円
これらはあくまで平均値であり、企業の業績や個人の役職によって変動します。
退職金の計算方法
退職金の金額は、企業ごとの「退職金規程」に基づいて計算されます。主な計算方法は以下の3つです。
1. 給与比例方式
退職時の基本給に勤続年数に応じた支給率を掛けて計算します。
計算式:退職時基本給 × 勤続年数 × 支給率 例:基本給50万円、勤続30年、支給率40倍の場合 50万円 × 30年 × 40% = 600万円
2. 定額方式
勤続年数に応じて固定額を支給する方式です。中小企業でよく採用されます。
例:勤続1年につき10万円、勤続30年の場合 10万円 × 30年 = 300万円
3. ポイント方式
勤続年数や役職に応じてポイントを付与し、ポイント単価を掛けて計算します。
計算式:ポイント合計 × ポイント単価 例:ポイント合計100、単価1万円の場合 100 × 1万円 = 100万円
実際の計算は企業によって異なり、自己都合退職と会社都合退職で支給率が変わる場合もあります。詳細は就業規則や人事部に確認しましょう。
退職金に影響する要因

退職金の金額は、以下のような要因によって変動します。
勤続年数
勤続年数が長いほど退職金は多くなります。ただし、勤続年数が短い(例:3年未満)場合は、退職金が支給されない企業も多いです。
退職理由
自己都合退職(転職や早期退職など)よりも、会社都合退職(リストラや倒産など)のほうが退職金が高く設定される場合があります。
企業の規模・業績
大企業や業績が好調な企業は、退職金が手厚い傾向があります。一方、業績が悪い企業では退職金が削減されるリスクもあります。
役職
管理職や役員は、一般社員よりも高い退職金が支給されることが多いです。
退職金の税金と受け取り方の注意点
退職金は「退職所得」として課税対象ですが、給与所得に比べて税制上の優遇があります。
退職金の税金計算
退職金の課税額は以下の計算式で求められます。 課税退職所得金額 =(退職金 – 退職所得控除額)÷ 2 退職所得控除額:
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)
例:勤続30年、退職金2000万円の場合 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(30年 – 20年)= 1500万円 課税退職所得金額 =(2000万円 – 1500万円)÷ 2 = 250万円
この250万円に所得税・住民税が課されますが、控除額のおかげで税負担は軽減されます。
受け取り方の選択
退職金は一時金として受け取るか、年金形式で受け取るかを選べる場合があります。
- 一時金:まとめて受け取るため、税金の優遇が受けやすい。
- 年金:分割で受け取るため、毎年の税負担が抑えられるが、運用リスクがある。
どちらが得かは、退職金の金額やライフプランによって異なります。ファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
退職金がない場合の対処法
すべての企業が退職金制度を導入しているわけではありません。退職金がない場合、以下のような方法で老後の資金を準備しましょう。
個人年金保険
自分で積み立てる年金保険に加入することで、退職後の収入を確保できます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは自分で運用する年金制度で、掛け金が全額所得控除の対象となるため節税効果もあります。
NISA
つみたてNISAや一般NISAを活用して、投資で資産を増やすのも有効です。
退職金を賢く活用する方法

退職金を受け取った後は、計画的に活用することが重要です。以下は活用例です。
- 生活費の補填:退職後の生活費や医療費に充てる。
- 住宅ローンの返済:残債を一括返済して負担を減らす。
- 投資:余裕資金を投資信託や不動産に投資して増やす。
- セカンドライフの充実:旅行や趣味に使う。
ただし、退職金は一度きりの大きな資金です。衝動的な支出を避け、長期的な視点で計画を立てましょう。
まとめ 退職金の金額を知って計画を
「退職金 いくらもらえる」は、勤続年数や企業の制度によって大きく異なります。平均的には大企業で2000万円前後、中小企業で1000万円前後が目安ですが、詳細は就業規則や人事部で確認が必要です。また、税金の優遇や受け取り方の選択を賢く活用することで、手元に残る金額を最大化できます。
退職金は老後の生活を支える重要な資金です。早めに制度を把握し、退職金がない場合はiDeCoやNISAを活用して準備を進めましょう。将来の安心のために、今から計画を立てておくことをおすすめします。






















