「退職代行」と検索すると、「退職代行 危険」とサジェストがでてきて、不安な気持ちになりますよね。「トラブルに巻き込まれるかも」「違法じゃないの?」と心配する18歳〜35歳の皆さんに向けて、退職代行サービスのリスクとその回避方法を解説します。実際の経験談や法的根拠を基に、安心して利用できる理由をお伝えします。
退職代行サービスとは? 「危険」と言われる背景

退職代行サービスは、あなたに代わって会社に退職の意思を伝え、手続きを進めてくれるサービスです。上司に直接「辞めます」と言うのが難しい場合でも、専門家が対応してくれるので、精神的な負担が減ります。
でも、なぜ「危険」と検索されるのか? その背景には、「詐欺業者がいる」「会社から訴えられるかも」といった噂があります。本当のところはどうなのか、具体例を交えて見ていきましょう。
利用者の経験談:成功例と失敗例

成功例
失敗例
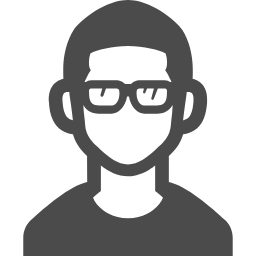
Bさん(32歳、元事務職)は、安さにつられて選んだ代行サービスで失敗。「途中で業者の連絡が途絶えて、会社から直接電話がかかってきた。結局自分で交渉する羽目に…」。この場合、業者が法的に問題のある対応をした可能性があり、サポートが不十分だったのが原因です。
厚生労働省の調査(2020年)によると、パワハラに関する相談は年間約7万件もあり、退職代行の需要が高まっていることが分かります(厚生労働省, 2020)。
退職代行の法的リスクと「危険」の真相

法的リスク1:非弁行為
非弁行為とは、弁護士資格がない人が法律に関する交渉などを代行することです。弁護士法第72条で禁止されており、違反すると業者が罰せられる可能性があります(弁護士法, 1949)。たとえば、給料未払いの交渉や退職条件の変更を弁護士以外が行うと、このリスクが浮上します。
回避方法
弁護士が監修しているか、直接対応するサービスを選びましょう。信頼できる業者は「非弁行為に該当しない範囲で代行します」と明言しており、リスクを回避しています。
法的リスク2:退職の無効
労働基準法第26条では、退職の2週間前に申し出れば、労働者は自由に辞められる権利があります(労働基準法, 1947)。でも、会社が「引き継ぎがないと認めない」と主張することもあります。法的には、退職は労働者の権利なので、会社が拒否することはできません。
回避方法
代行会社が労働基準法に沿った手続きをしてくれるので、退職が無効になる心配はありません。信頼できる業者は、法的な根拠をしっかり説明してくれます。
信頼できる退職代行会社の選び方
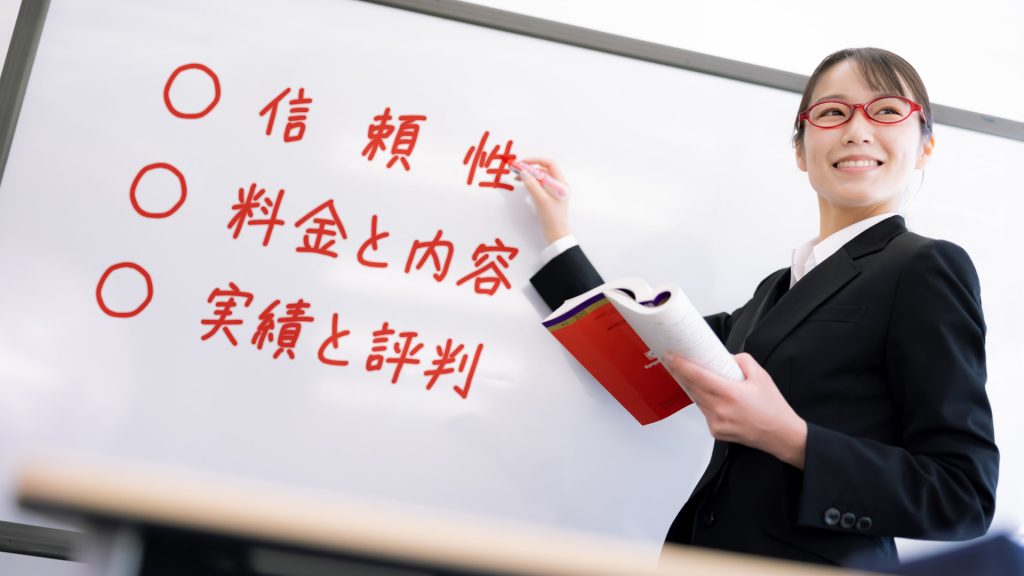
「危険」を避けるには、業者選びがカギです。以下のポイントをチェックしてください。
Cさん(24歳、元エンジニア)は、「弁護士監修のサービスを選んだら、会社からの文句もなく安心して辞められた」と話します。しっかり選べば、リスクはぐっと減ります。
退職代行会社が取っている「安心」対策

信頼できる業者は、こんな対策を取っています。
総務省のデータ(2021年)によると、正社員の離職率は15%程度で、特に20代〜30代前半で高い傾向があります(総務省統計局, 2021)。辞めづらい環境にいる若者にとって、退職代行は安心できる選択肢の一つです。
退職代行は「危険」ではなく「賢い選択」
退職代行の「危険」は、信頼できない業者を選んだり、法的な知識がない場合に起こりがちです。でも、弁護士監修のサービスを使い、労働基準法に基づいた手続きをすれば、ほぼリスクはありません。パワハラや過労から自分を守る手段として、退職代行は賢い選択です。
18歳〜35歳の皆さん、もし辞めたくて悩んでいるなら、信頼できる退職代行を検討してみてください。自分の心と体を大切に、安心して一歩踏み出しましょう。
参考資料
厚生労働省, 2020: パワハラ相談件数/弁護士法, 1949: 非弁行為について/労働基準法, 1947: 退職の自由/総務省統計局, 2021: 離職率データ

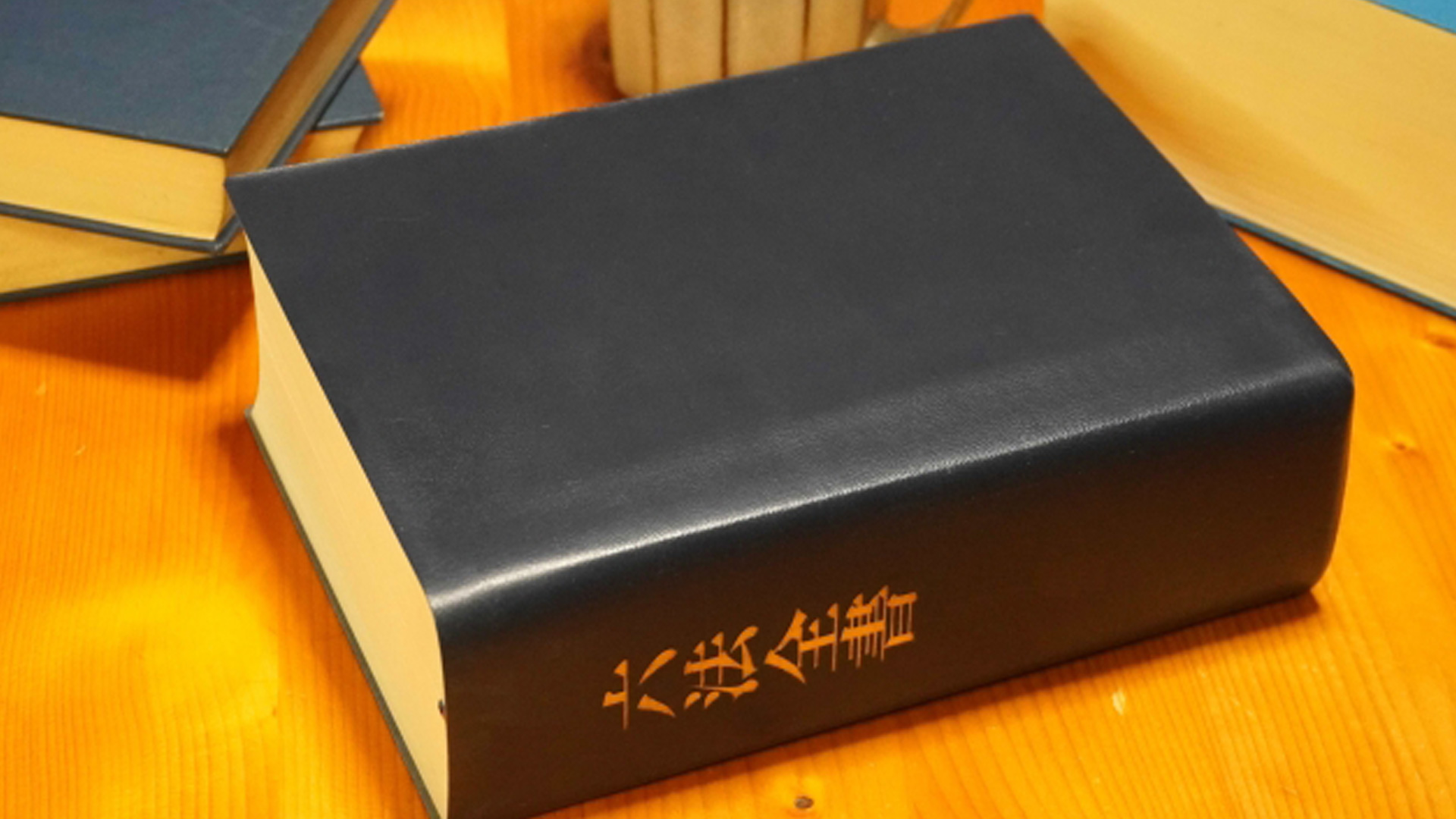



















Aさん(27歳、元販売員)は、パワハラを受けていた職場を退職代行で辞めました。「自分で辞めると言ったら何をされるか怖かったけど、代行会社が全部やってくれて、2週間でスムーズに退職できた。給料もちゃんと振り込まれた」とのこと。信頼できる業者を選んだことで、安心して次のステップに進めました。