退職代行サービスを利用する若者(18歳〜35歳程度)が増える中、一部の経営層から「そんなサービスを使うなんてクズだ」と批判されることがあります。でも、本当にそうでしょうか?
この記事では、退職代行サービスがなぜ必要なのか、法的リスクはないのか、そして安心して利用できる理由を、経験談やデータも交えて解説します。労働者の権利と義務のバランスも考慮しながら、「クズ」というレッテルが誤解に基づいていることをお伝えします。
退職代行サービスとは? 「クズ」と言われる風潮

退職代行サービスとは、自分で会社に退職を伝える代わりに、専門の会社や弁護士が退職手続きを代行してくれるものです。例えば、「もう限界…」と感じたときに、気まずい対話を避けてスムーズに辞められるサービスです。
しかし、一部の経営者や上司からは、「直接言わずに逃げるなんて無責任」「クズだ」と見られることがあります。背景には、「会社に迷惑をかける」「最後まで自分でケジメをつけるべき」という考えがあるようです。でも、この見方は一方的すぎませんか? 実際のところ、退職代行が必要になる状況を考えてみましょう。
「クズ」と言われた経験談とその背景

例えば、Aさん(25歳、元営業職)のケース。Aさんは上司からのパワハラに耐えきれず、退職代行を利用しました。
「毎日怒鳴られて、心がボロボロだった。直接辞めると言ったら何されるか分からないから、代行に頼った」と話します。退職後、元同僚から「上司が『あいつはクズだ』って言ってたよ」と聞きました。でも、Aさんは「自分を守るために選んだだけ。後悔はない」と言います。
厚生労働省の調査(2020年)によると、パワハラに関する相談は年間約7万件以上(厚生労働省, 2020)。過重労働や人間関係のストレスで辞めたくても言えない人は少なくありません。「クズ」と呼ぶのは簡単ですが、そうせざるを得なかった背景を見逃していませんか?
退職代行が必要な理由

退職代行が「逃げ」ではなく「助け」になるケースは多いです。例えば:
総務省のデータ(2021年)では、正社員の離職率は15%程度で、特に20代〜30代前半で高い傾向があります(総務省統計局, 2021)。若い世代はキャリアチェンジも多いですが、辞めづらい環境がそれを阻むことも。退職代行は、そんな人たちにとって安全な出口なんです。
法的リスクはある? 安心できるポイント

「退職代行って違法じゃないの?」と思う人もいるかもしれません。でも、心配いりません。
労働基準法第26条では、労働者は退職の2週間前に申し出れば自由に辞められると定められています(労働基準法, 1947)。退職代行サービスは、このルールに従って手続きを進めるので、法的には全く問題なし。会社が「訴える」と脅しても、法律上は労働者の権利が守られています。
ただし、例えば「引き継ぎをしないと損害賠償を請求する」と言われるケースも稀にあります。でも、裁判所の判例(例:東京地裁平成28年)では、引き継ぎ不足での賠償請求が認められるのは極めて例外的な場合だけ。普通の会社員ならまず大丈夫です。
退職代行会社の対応で安心感アップ

退職代行会社は、ただ辞める手続きを代行するだけじゃないんです。例えば:
Bさん(30歳、元事務職)は、「代行会社が会社と連絡を取ってくれて、給料未払いの交渉までしてくれた。自分で言わなくて済んだからストレスが減った」と振り返ります。ちゃんとした会社を選べば、トラブルなく辞められるんです。
労働者の義務と権利のバランス

もちろん、労働者には義務もあります。契約を守って働くこと、業務を引き継ぐ努力をすることは大切です。でも、義務を果たす一方で、自分の心や体を守る権利だってあります。
例えば、労働基準法では「安全で健康的な労働環境」が保障されています(労働基準法第5条)。ブラックな職場で我慢し続ける義務はないんです。退職代行は、その権利を行使する一つの方法。「無責任」と決めつけるのは、労働者の現実を見ていない意見かもしれません。
「クズ」じゃない、賢い選択
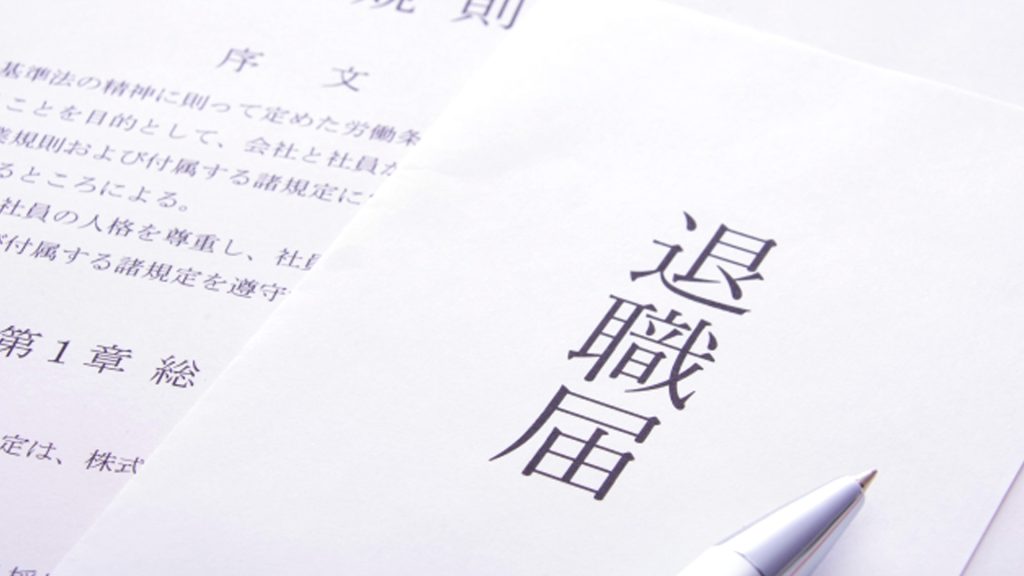
退職代行サービスを使う人は「クズ」ではなく、自分を守るために行動した人たちです。パワハラや過重労働から逃れるため、法律に基づいて安全に辞める手段として、退職代行は大きな助けになります。法的リスクはほぼなく、信頼できる代行会社を選べば安心です。
「クズ」と呼ぶ風潮は、労働者の苦しみを無視した誤解。18歳〜35歳のみなさん、もし辞めたくて悩んでいるなら、退職代行も選択肢の一つとして考えてみてください。義務を果たしつつ、自分の人生を守るのは、決して恥ずかしいことじゃないですよ。
参考資料
厚生労働省(2020年) パワハラに関する相談件数についてのデータ/総務省統計局(2021年) 正社員の離職率に関するデータ/労働基準法(1947年) 退職に関する法的根拠





















