仕事をやめる決意はつらく、言葉にするのはもっとつらい。そんなとき、第三者に「会社への連絡」を任せられる退職代行は便利です。しかし、サービスの“安心度”は運営主体で大きく変わります。
最新のインターネット調査では、民間業者による対応が法的問題(非弁行為)に発展する例が増えているとして、弁護士会からも注意喚起が出されています。まずは運営主体の違いと、弁護士が運営することの強みを整理しましょう。
弁護士監修と弁護士運営とは?退職代行の違い
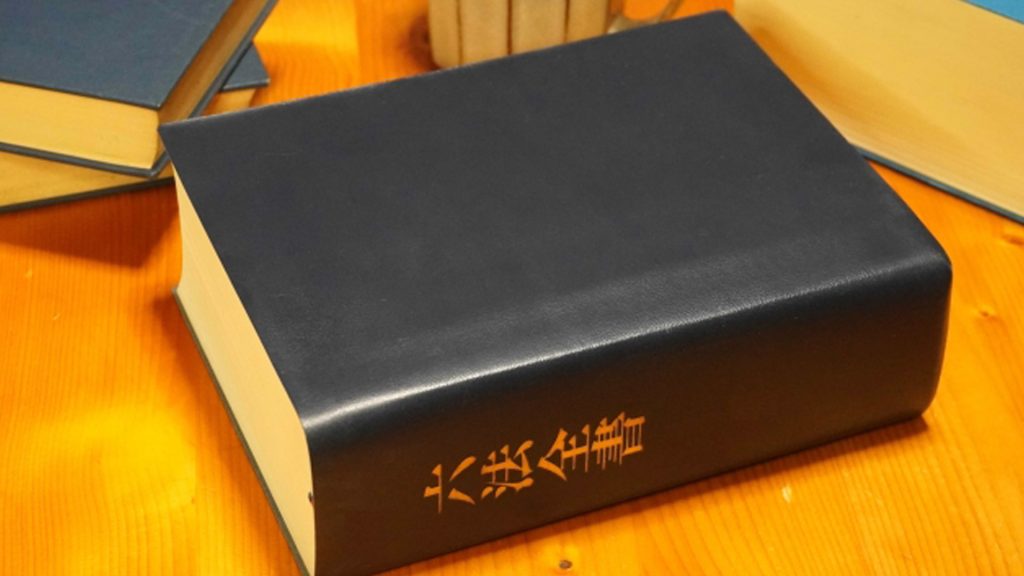
まず押さえるべき法的背景 — 非弁行為(弁護士法)
報酬目的で法律事務(示談交渉、請求、代理、和解など)を業として行えるのは原則として弁護士だけです。弁護士資格のない業者が、実務的に「未払賃金の請求」や「示談交渉」を代行すると、弁護士法に抵触する(=非弁行為)可能性が高く、弁護士会からも注意喚起が出ています。
1. 弁護士(弁護士法人)運営
2. 労働組合運営(ユニオン型)
3. 民間業者(いわゆる退職代行会社)
「弁護士監修」と表示されるサービスについて
リスク 監修のみで実務は非弁者が行っていると、会社側が交渉を拒否したり、後で「非弁行為」として問題になる可能性があります。
実態 多くの場合「監修」は弁護士が文面や手順のリーガルチェックを行ったに過ぎず、運営主体は民間業者のままです。監修がある=弁護士が交渉・代理を担う、とは限りません。弁護士の関与の深さ(実際に交渉に出るか、常駐しているか)を必ず確認する必要があります。
退職代行に弁護士運営を強く勧める理由

- 法的代理が可能
未払い残業代や退職金請求、損害賠償請求といった法的請求は「法律事務」に当たります。弁護士であれば正式な代理人として会社と交渉し、必要なら労働審判・訴訟へ移行できます。民間業者ではこれができず、結果的に回収や解決が遠のくことがあります。 - 非弁行為のリスク回避
弁護士会は、弁護士資格を持たない業者や提携先への「仲介」で生じる非弁行為について警鐘を鳴らしています。弁護士運営ならこの点で安全性が高く、後から「違法だった」と揉めるリスクを減らせます。 - トラブル時の対応力
交渉で決着しない場合、書面作成や強制執行など法的手続きが必要になるケースがあります。弁護士が窓口であれば、手続きの切替えがスムーズで、結果として回復できるケースが増えます。 - 証拠・記録の扱いと守秘義務
弁護士は守秘義務の対象であり、やり取りの記録や証拠を適切に扱えます。心理的にも「公的な専門家に任せている」実感が得られる点は見落とせません。
退職代行のサービスにどんな差が出るか
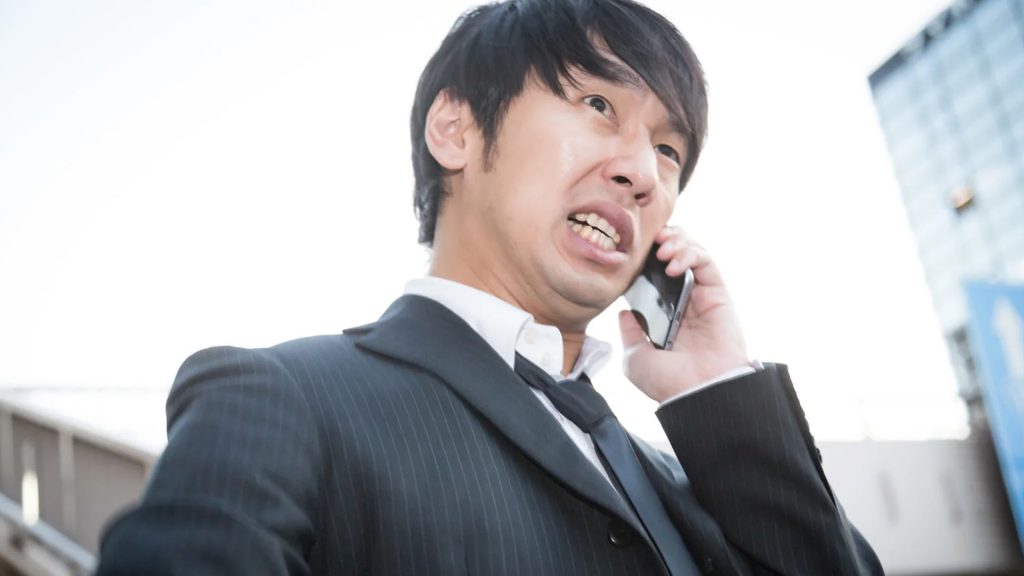
退職代行を利用前に確認すべきこと

それでも「まずは相談」してみてほしい理由

退職は感情が先行しやすく、判断が孤立しがちです。公的窓口(総合労働相談コーナーや労働条件相談ほっとライン)での相談も有効ですが、金銭請求や法的対応が必要な可能性があるなら、初期段階で弁護士に相談しておくと選択肢が広がります。公的相談窓口は法令違反の有無を確認する一次対応として便利です。
弁護士運営を強く勧める最後の一言
「言えない」「出社したくない」と感じるのは決して弱さではありません。問題が単なる意思表示で終わるのか、法的な争いに発展し得るのかはケースバイケースです。
最新のインターネット調査が示す通り、運営主体によって後の安心度が大きく変わります。法的争いの可能性が少しでもあるなら、弁護士が運営する退職代行を選ぶことを強くおすすめします。弁護士はあなたの代わりに正当に「権利」を主張できる唯一の専門家です。
出典(参考・引用)
- 東京弁護士会「退職代行サービスと非弁行為に関する解説」など。
- 朝日新聞「退職代行 利用拡大と弁護士会の注意喚起」。
- 弁護士法人みやび(公式サイト)
弁護士法人みやび
- 厚生労働省 労働条件相談・総合労働相談コーナー案内。
- 労基署・弁護士関連解説(未払い残業代の回収に関する解説記事)。





















