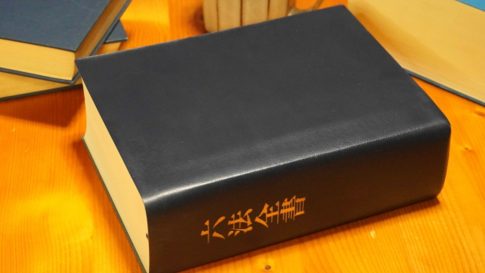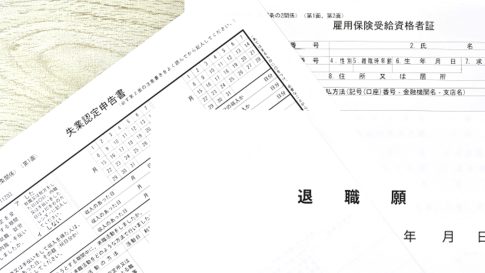退職代行を巡る報道が増えており、若年層の利用動向や企業側の対応、弁護士会の注意喚起など注目すべきテーマが次々と浮上しています。
ここでは(1)弁護士会の警告、(2)業界データの公開、(3)トラブル事例、(4)弁護士運営サービスの台頭、(5)メディア・SNSの影響、の5点を分かりやすく整理し、実務上の示唆も併せてご紹介します。
東京弁護士会などの注意喚起 「非弁行為」のリスク 2025年7月発表

最近の報道で特に重いのは、2025年7月に東京弁護士会が退職代行に関し「内容次第では弁護士法違反(非弁行為)となるおそれがある」との見解を示した点です。これは業界全体に対する法的リスクの再認識を促す重要なメッセージであり、サービス選びの基準にも直結します。
たとえば、未払い賃金の算定や交渉を民間業者が行うことは非弁行為に該当すると明記しており、業界に対する法的リスクの再認識を促す重大な声明でした。サービス利用者としては、「弁護士監修」と「弁護士運営」の違いを明確に確認する必要性が高まりました。
業界データの公開と利用拡大の傾向

代行業者や関連企業が公表するデータでは、特に若年層(新卒・20代)の利用が相対的に高く、長期休暇明けや年度替わりに相談が集中する傾向が確認されています。
PR TIMESなどのプレスでは、各社が年度別の集計結果を出し、サービスの認知度と利用実態が年々上がっていることを示しています。これらの公開データは、利用者ニーズの可視化と同時に、事業者側の対応改善を促す材料になっています。
利用トラブルの報道事例―負担と企業リスクの見え方

一方で、退職代行を介したやり取りで会社側とトラブルになるケースも報道されています。行政・労働相談や当事者の証言をもとに「退職は成立したが、それ以降の金銭トラブルや手続き上の行き違いが生じた」という事例が散見され、個人にとっては精神的負担が続く場合があります。
企業側も未払賃金の発覚や訴訟リスクが表面化すると信用問題に発展し得るため、双方にとって慎重な対応が求められます。
弁護士運営サービスの台頭と差別化要因
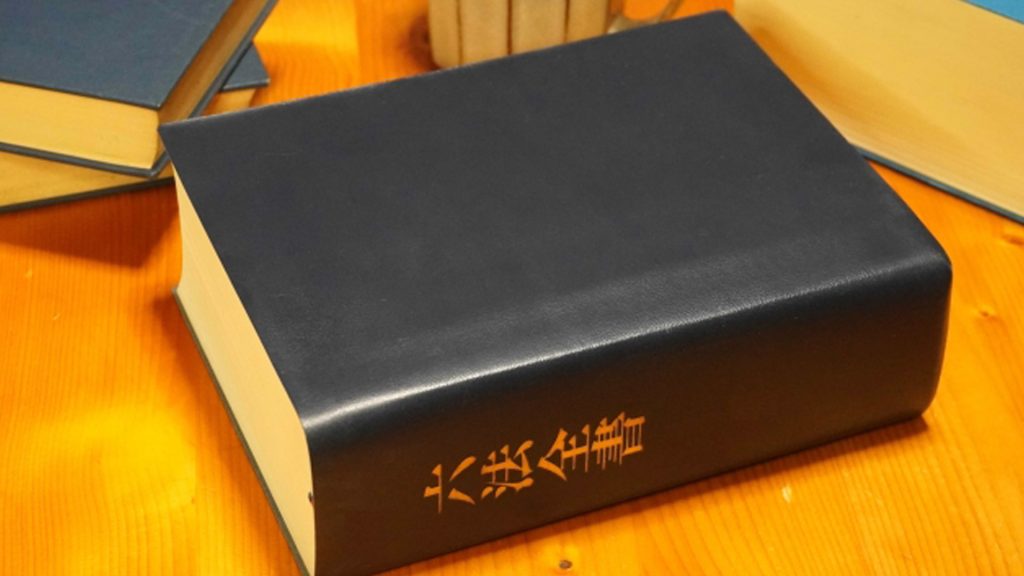
こうした環境のなか、弁護士が運営する退職代行サービスの注目度が上がっています。弁護士運営であれば、依頼者の代理人として未払い賃金や有給消化などの交渉が可能であり、非弁リスクも回避できます。
複数メディアで紹介されている事務所の事例では、法的代理ができることが“安心”の根拠として評価されています。費用は一般業者より高めでも、トラブルに発展した際のワンストップ対応力が選ばれる理由です
弁護士法人みやびによる退職代行サービス
最新ニュースでも注目されるのが、弁護士法人みやびによる退職代行です。多くのメディアや比較サイトでも取り上げられているように、みやびでは弁護士が窓口となり、退職の意思表示から交渉、有給取得・未払い賃金・退職金請求まで、法的範囲で一貫したサポートが提供されます。
その結果として、「退職後のトラブル回避」「精神的な安心感」がユーザーから高く評価されており、他の民間代行と比較して“安心の証”として位置づけられています。必要であれば、実際の相談フローや料金事例を紹介することもできます。
弁護士法人みやび(公式サイト) 弁護士法人みやび
メディアとSNSの影響─情報拡散が利用行動を後押し

YouTubeやSNSでの体験談や解説動画が増え、退職代行が「選択肢」として広く浸透しています。メディア報道は需要をさらに可視化し、相談の心理的ハードルを下げる効果をもたらします。ただし、オンライン情報だけで判断すると、運営主体や対応範囲の見誤りに繋がるため、情報の出どころを確認することが重要です
ニュースから見える業界の当面の課題と利用者への示唆
- 法的境界線の明確化が急務:弁護士会の指摘を踏まえ、業界全体で「何が非弁か」を明示するポリシー整備が必要です。利用者にわかりやすく示す必要があります。また利用者は「弁護士監修」と「弁護士運営」の違いを確認しましょう。
- 透明な料金・対応範囲の提示:ニュースで問題になった事例の多くは「できること・できないこと」の認識齟齬に起因しています。事業者はサービス範囲を明確に示すべきです。料金や対応範囲の認識齟齬はトラブルの温床となるため、業者側は事前に明瞭に示すことが重要です。
- 弁護士運営の存在感:法的対応が必要なケースでは弁護士運営が安心材料になります。費用対効果を見極めた上での選択が賢明です。未払い賃金やトラブル発展の可能性があるなら、多少費用がかかっても弁護士運営を選ぶ価値があります。
退職代行の利用を考える人への実務的チェックリスト
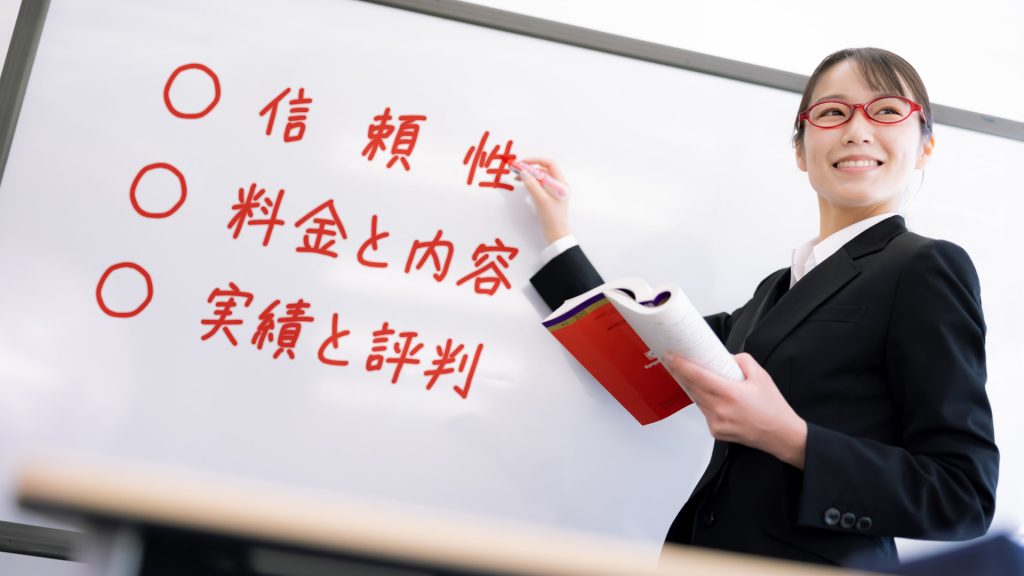
結び — ニュースは「防衛」と「改善」の礎になる
報道で明らかになった通り、退職代行は救いの手であると同時に、法的・手続的リスクを伴う選択肢です。ニュースに表れている課題は、どのサービスを選ぶかが結果を分けることを示しています。
自分の目で運営主体や対応範囲を確かめた上で、必要とあれば弁護士運営を選ぶのが最も確実な安心策です。
出典(本文で参照した主な報道・資料)
- 朝日新聞「若者で広がる退職代行 でも、実は違法? 弁護士会が異例の注意喚起」。
- 東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反に関する解説」。
- PR TIMES(複数会社の退職代行関連プレスリリース)。
- Manegy「退職代行における弁護士の役割とは?」(業界インタビュー)。
- 弁護士法人みやび・サービス紹介記事および比較記事(メディア掲載)。
- 各マスメディア・ブログ・YouTube等の関連報道・解説。