「退職代行」とは、従業員が直接雇用主と対峙せずに退職手続きを代行するサービスです。日本では、特に20代を中心とする若年層で利用が急増しています。2024年のマイナビキャリアリサーチラボの調査によると、過去1年間に転職した人の16.6%が退職代行を利用し、20代ではその割合が18.6%に上昇しています。
この背景には、職場でのパワーバランスの不均衡やコミュニケーションの障壁が存在します。特に、長時間労働やハラスメントが常態化する「ブラック企業」からの脱出手段として注目されています。
企業視点:退職代行がもたらす課題

企業にとって、退職代行は予期せぬ影響を及ぼします。以下に具体的な問題を挙げます:
- 業務の混乱
重要なポジションの従業員が突然退職すると、業務が停滞します。例えば、東京商工リサーチ(2024年)の調査では、大企業の18.4%が退職代行を経験し、特にサービス業で影響が顕著でした。ある飲食チェーンでは、繁忙期に複数のパートタイム従業員が一斉に代行経由で退職し、顧客対応が追いつかなくなった事例が報告されています。 - 不公平感の増幅
日本では労働契約法第16条により、企業が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由」が必要で、解雇規制が厳格です。一方、民法第627条に基づき、従業員は2週間の予告で退職可能。この法的非対称性が、企業側に「従業員は簡単に辞められるのに、企業は縛られている」という不満を生んでいます。 - 知識移転の欠如
IT企業でリードエンジニアが代行経由で退職したケースでは、後任への引継ぎがなく、プロジェクトが数カ月遅延しました。こうした事例は、企業が退職代行を「無責任」と捉える一因です。
従業員視点:退職代行を選ぶ理由

従業員が退職代行を利用する背景には、以下のような切実な事情があります:
- 対立への恐怖
エン・ジャパン(2024年)の調査では、利用者の32.4%が「直接退職を伝えにくい」と回答し、23.7%が「退職後のトラブル」を恐れていました。上司からの引き留め圧力や感情的な報復が懸念される場合、代行は「安全な出口」となります。 - 精神的負担の軽減
過労やパワハラに耐えかねた従業員にとって、代行は心理的救済手段です。例えば、ある20代の販売員は「上司に精神的に追い詰められた」と述べ、代行を利用して退職。その後、心身の回復に専念できたと報告しています。 - 自己主張の困難さ
日本特有の「和を重んじる」文化が、退職の意向を直接伝えるハードルを高めています。特に若手は、上司との力関係で声を上げにくい状況に置かれがちです。
法的側面:グレーゾーンとリスク
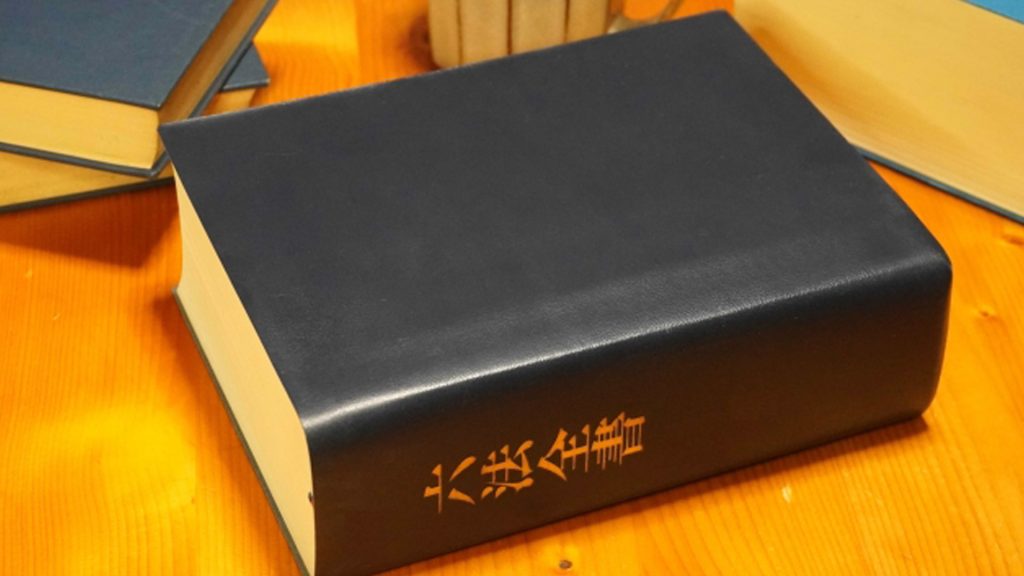
退職代行の合法性は複雑です。以下にポイントを整理します:
- 退職の自由
民法第627条により、無期雇用契約の従業員は2週間の予告で退職可能。固定期間契約でも、民法第628条の「やむを得ない事由」があれば退職できます。代行業者が単なる「伝達役」である限り、法的に問題はありません。 - 非弁行為のリスク
弁護士法第72条では、非弁護士が報酬を得て法的な交渉を行うことは禁止されています。退職代行業者が未払い賃金の請求や条件交渉を行うと「非弁行為」に該当し、東京弁護士会(2024年)はこれを違法と警告。弁護士や労働組合が運営するサービス以外は法的リスクを伴います。 - 法的紛争の可能性
企業が代行経由の退職を「無効」と主張し、訴訟に発展するケースも。ある小売業では、退職の意思確認が不十分として争われ、従業員側が追加手続きを強いられました。
実例から見る影響

- 企業側の危機
中小IT企業では、プロジェクトリーダーが代行で退職し、専門知識の引継ぎがゼロに。クライアントとの契約違反に繋がり、損害賠償を検討する事態となりました。 - 従業員の救済
ある製造業の従業員は、長時間労働と上司の暴言に耐えかねて代行を利用。退職後、労働基準監督署に相談し、未払い残業代を請求する準備を進めました。
不公平感の根源と解決策

退職代行が浮き彫りにするのは、職場における力の不均衡です。企業はリソースと法的保護を持ち、従業員は自己主張が難しい。このギャップを埋めるには:
- 企業側
- オープンな対話の場を設ける。マイナビ調査では、60%の利用者が「職場が話しやすければ代行は不要」と回答。
- 退職プロセスを明確化し、管理職に適切な対応を教育。
- 従業員側
- 可能な限り直接対話を試み、誤解を防ぐ。
- 代行利用時は、弁護士運営のサービスを選び法的リスクを回避。
結論
退職代行は、職場力学の歪みと不公平感を映し出す鏡です。従業員には退職の自由がある一方、企業は法的・運用上の制約に直面します。この問題を解消するには、相互理解とコミュニケーションの改善が不可欠です。代行は一時的な解決策に過ぎず、職場環境の根本的な改革が求められます。
参考資料
- マイナビキャリアリサーチラボ「退職代行サービス利用調査(2024年)」
- 東京商工リサーチ「企業における退職代行の影響」
- エン・ジャパン「退職代行利用実態調査」
- 東京弁護士会「退職代行サービスの法的問題点」



















