SNSでは「退職代行なんてありえない」「最後ぐらい自分で言うべき」といった強い言葉が流れます。一方で、退職の自由は法律で保障されており(期間の定めのない雇用は「申し入れ後2週間で終了」)、制度や運用を知ると、過度に自責する必要がない場面も見えてきます。
「ありえない」と言われがちな理由と、その実態

1) 礼を欠く/人としてどうか
感情の問題として語られがちですが、法律は“手続の適法性”を基準に判定します。退職の意思表示は本人が行うのが原則でも、連絡の媒介や伝達自体は違法ではありません(違法になり得るのは“交渉の代理”の領域。後述)。
2) 会社が絶対に許さない
退職は会社の許可制ではありません。民法の規定に従って退職は成立し得ます。もっとも、有期契約の途中は「やむを得ない事由」が必要で、個別事情の吟味が必要です。
3) 有給なんて取れない
年5日の取得確保は使用者の義務。加えて労働者には時季指定権があり、会社は事業運営を妨げる場合に限って時季変更権を行使できます。原則として「取れない」ではなく、「日程を調整する」のが法の建付けです。
4) 退職代行を使うと訴えられる
利用それ自体が損害賠償の理由にはなりません。トラブルは別の要因(無断欠勤の長期化、競業避止義務、貸与物の未返却など)から派生することが多い、という弁護士解説が複数あります。
5) ハラスメントは我慢すべき
厚生労働省はハラスメントの予防・相談を明確に推奨し、外部窓口の活用を案内しています。追い詰められているなら、まずは相談で状況を言語化しましょう。
どこから「違法っぽさ」が出てくるのか 非弁リスクについて
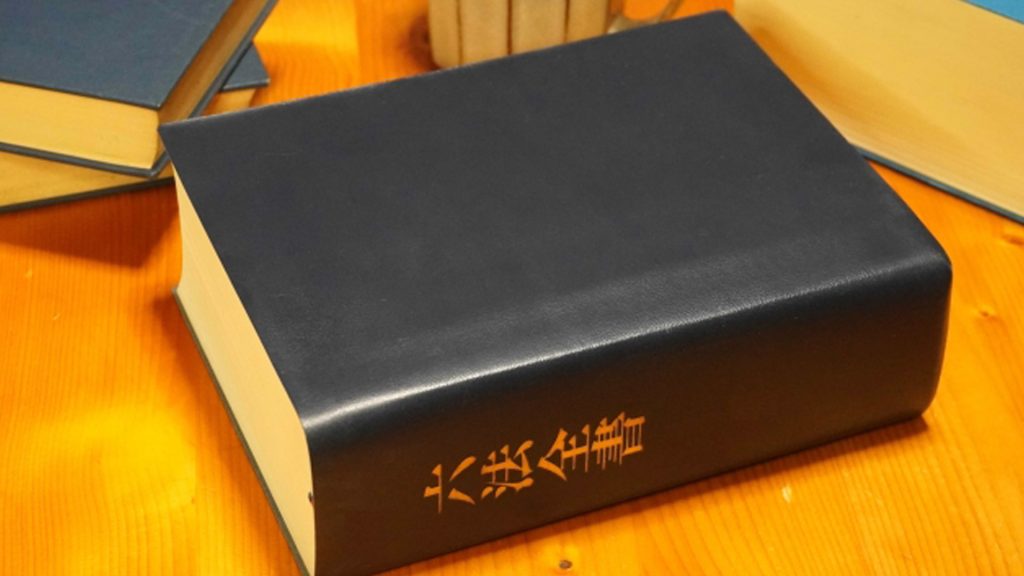
退職代行が問題視される最大のポイントは、“交渉”の代理を巡る非弁行為のリスクです。賃金・有給・損害賠償など法律上の権利義務に関わる交渉は弁護士の業務領域であり、民間事業者が受任・斡旋するのは非弁に当たるとの指摘があります。
依頼料を受け取り、法的問題の処理を他者に斡旋するケースも非弁該当と解され得ると弁護士会が解説しています。
したがって、「連絡の代行」と「交渉の代理」を厳密に分ける運用か、弁護士(または労働組合の適正な団体交渉)の関与が明確なスキームかを確認するのが要点です。
実際に起こりやすいトラブルの傾向

使う前に整える「3つの土台」

- 法的な前提
- 期間の定めがない雇用:意思表示+2週間で終了。
- 有期契約途中:やむを得ない事由が原則必要。個別事情と証拠の整理を。
- 権利と運用(有給)
- 年5日の取得確保は会社の義務/時季変更は限定的。「取れない」ではなく「調整」が基本。
- 相談のセーフティネット
- **総合労働相談コーナー(全国・無料)**や労基署、ハラスメント窓口の活用。記録の持参が勧められています。
「ありえない」で切り捨てない、4つの選択肢

チェックリスト(申し込み前に)

それでも迷うときに:小さな一歩の踏み出し方
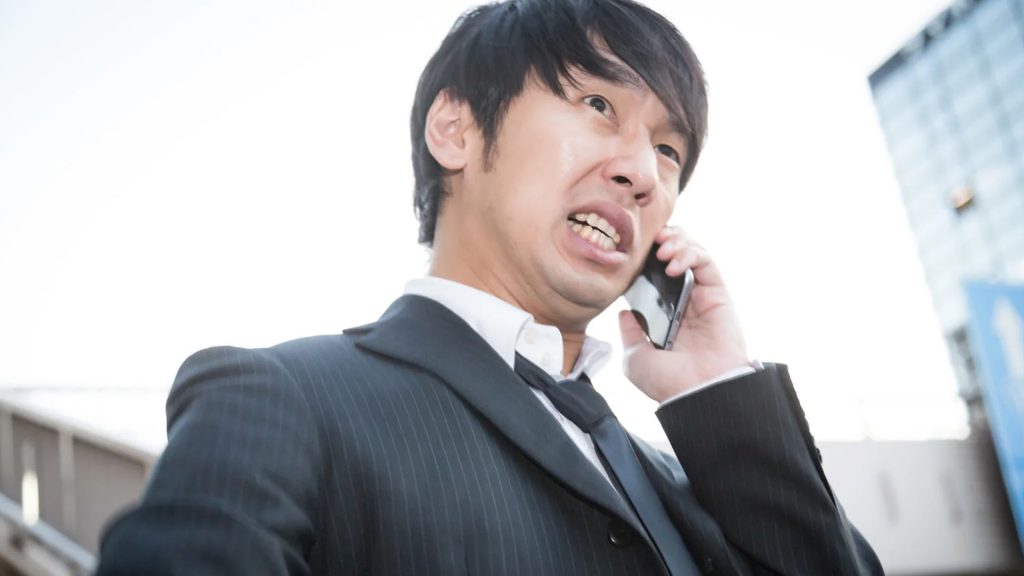
- 現状の事実をメモ(いつ・どこで・誰に・何を言われ/されたか)。相談時に役立ちます。
- 退職までの逆算カレンダー(郵送日数、貸与物返却、有給の時季調整)。
- 選択肢A〜Dを“明日できる行動”に分解(電話一本・相談予約・契約書確認)。
「ありえない」と自分を責めるより、安全に抜け出す設計に時間を使ってください。法の枠組みと公的支援は、あなたに“逃げ道”ではなく“正規ルート”を用意しています。
まとめ
退職代行は万能薬でも、悪でもない。法に沿った退職の自由、有給の取得原則、非弁の線引き、相談窓口の存在――この4点を押さえれば、感情論に振り回されず、自分に合った方法を選べます。まずは今日、相談窓口へ一本の電話、または契約書の確認から始めてみてください。
参考資料(公的・基礎情報)
- 民法627条・退職の申入れ、民法628条・有期契約の途中解除(各労働局解説)(都道府県労働局所在地一覧)
- 厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得/時季指定・時季変更の考え方(厚生労働省, 都道府県労働局所在地一覧)
- 厚生労働省(あかるい職場応援団):ハラスメントの定義・相談窓口案内(no-harassment.mhlw.go.jp)
- 北海道労働局:総合労働相談コーナー(札幌を含む一覧)(都道府県労働局所在地一覧)





















