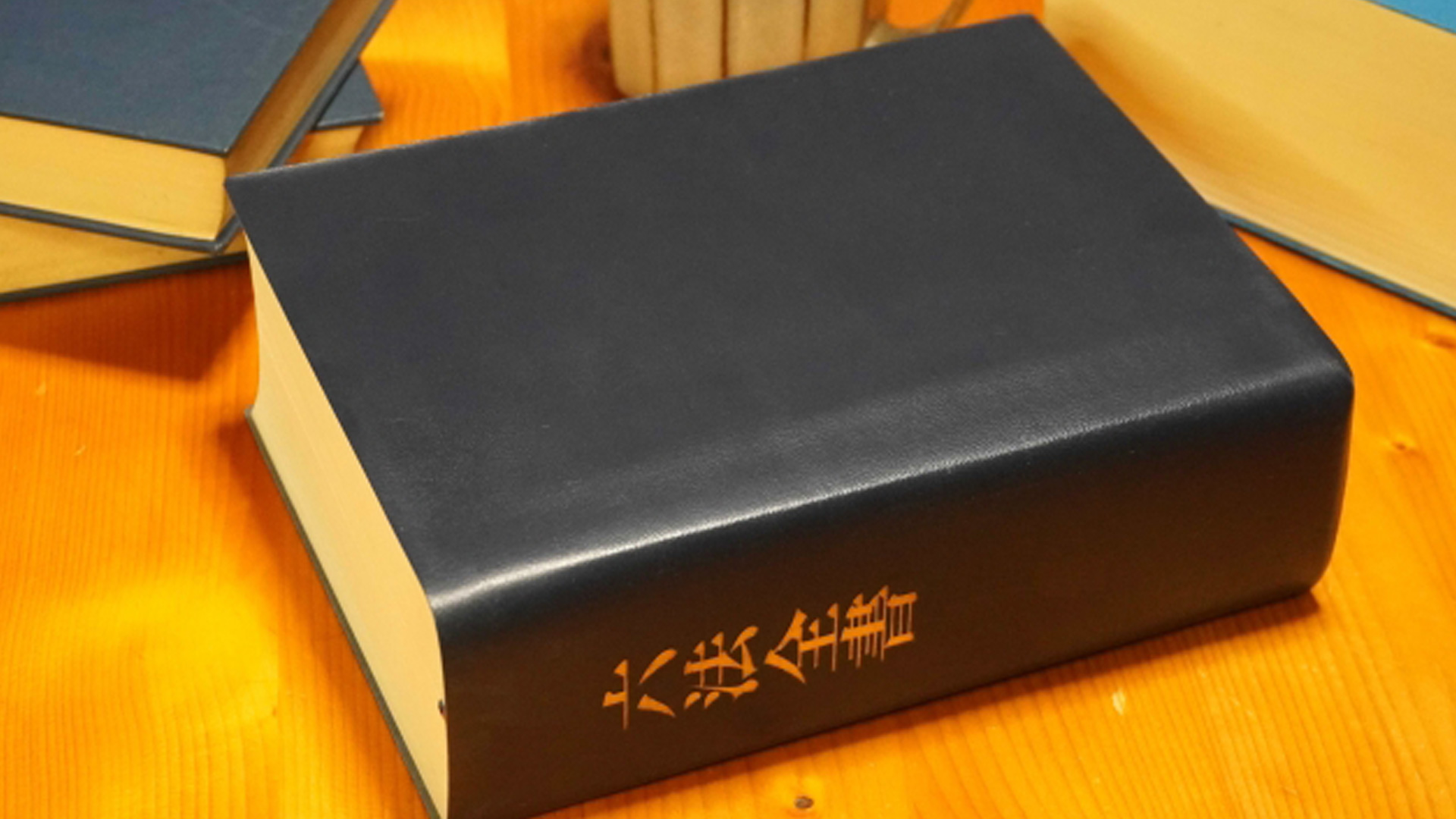退職代行と「非弁行為」──まず押さえる法的な原則
日本では、誰が「法律事務」を業として行えるかは弁護士法で限定されています。弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件(訴訟・示談・和解などを含む)について代理・交渉・鑑定・斡旋を業として行うことは禁じられています(弁護士法 第72条)。このため、退職に絡む「法律的な争点」を業として扱う際は特に注意が必要です。
「ここまでは問題ない」 民間業者が通常行って差し支えない範囲

- 退職の意思を会社に伝える連絡の代行/メッセンジャー
本人に代わって「退職します」と連絡したり、退職届やメールを代筆して送る行為そのものは、基本的には「事実の伝達」にとどまるため、直ちに非弁にはなりません(ただし表現次第で助言・交渉に見える場合は後述)。 - 事務的なサポート書類の書き方案内・郵送代行、退職手続きのチェックリスト提示など
手続きの進め方や書類の取り次ぎ、郵便代行など、法律的判断を含まない単純事務支援は一般的に許容されます。 - 労働局や労基署等、公的窓口への相談案内
どの窓口に相談すべきか案内することは問題になりません。
上の行為でも、表現が「○○すれば有給が確実に取れます」「未払いはこれだけあります」といった法律的判断・金額算定を含めると問題になります。
「ここからが非弁行為」 民間事業者がやってはいけない具体行為
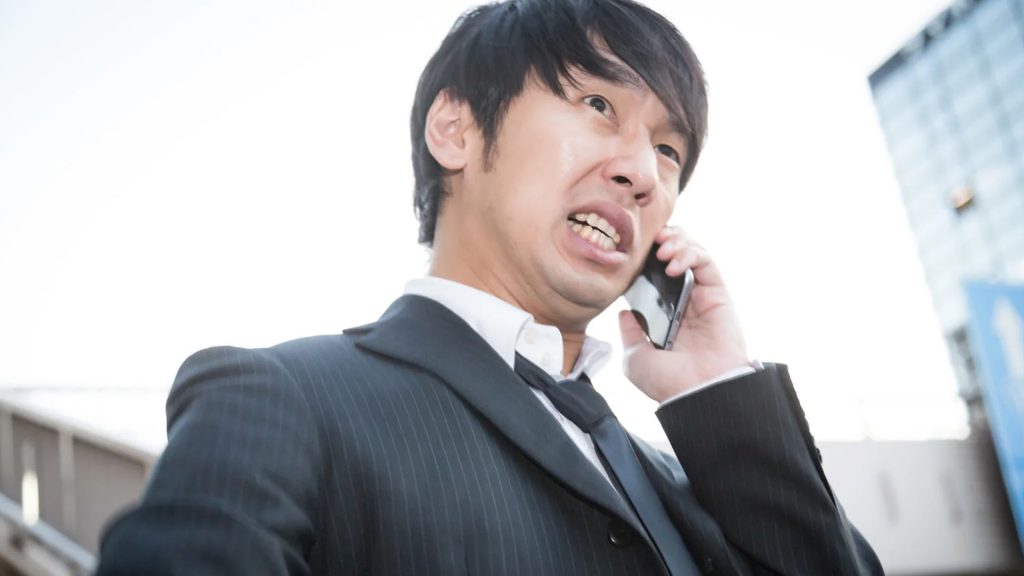
以下はいずれも弁護士や正当な代理権を持つ組織でない限り、業として行うと弁護士法違反(非弁行為)に該当する可能性が高い行為です。実務上、これらに踏み込む業者には強い懸念が示されています。
これらは「法律事件」を扱う行為に当たり、弁護士以外が業として行えば非弁に該当するリスクが高いとされています。事例解説でも、残業代の交渉を業者が行って支払が発生したケースは非弁として問題視されています。
「弁護士監修」は万能ではない なぜ『監修』だけでは足りないのか

近年の業者は「弁護士監修」「弁護士チェックあり」といった表現を用いますが、監修=弁護士が経営に関与している・最終的に責任を負っているとは限りません。監修とは多くの場合「文言チェック」「ガイドライン作成」という限定的関与に留まり、実際の交渉や個別事件の判断を弁護士が直接行っていないことが多いのです。
法の観点から重要なのは「誰が実務として代理・交渉を行うか」であり、弁護士が名義上の監修をしているだけでは、非弁行為の問題は解消されません。弁護士が実際に代理人として対応するか、弁護士法人が直接サービスを提供しているかがポイントです。法律団体もこの点を繰り返し警告しています。
労働組合を“窓口”にする形も注意が必要
「民間業者が仲介して利用者を労働組合に繋ぐ」モデルを採るサービスがあります。しかし、業者が金銭を受け取り労組に斡旋するような構図は問題視されることがあり、弁護士会からも警告が出ています。
実務上、労組が直接交渉権を持つ場合でも、仲介過程で金銭授受や実質的な代理行為が発生していれば非弁該当の疑いが生じ得ます。労組型だからといって自動的に安全とは言えません。
「実例」で見る線引き|よくある場面と判定目安
利用者が取るべき実務的対策 -契約前の必須チェック項目-

- 運営主体の確認:弁護士法人・弁護士個人が提供しているか。そうでない場合は弁護士が「直接」関与するかを確かめる。
- 業務範囲を明文化:「連絡代行のみ」「交渉は弁護士に委ねる」等、具体的に書面で確認する。
- 報酬と斡旋の流れを確認:利用料の受け取り先、労組や弁護士への送金フロー、追加費用の条件を明確にする。
- 交渉が必要になった場合のエスカレーション:弁護士へ切替える手順と費用を事前に取り決めておく。
- 記録を残す:やりとり(チャット・メール)や契約書のスクリーンショットは後で重要な証拠になります。
最後に
主な参考・出典
- 東京弁護士会:退職代行サービスと非弁行為に関する解説。飛天
- 労働系メディア(退職代行トラブル事例・業者比較)。労働問題弁護士ナビ
- 法律事務所による解説記事(非弁リスクと実務上の注意)。topcourt-law.com
- 厚生労働省:年次有給休暇、労働相談に関する制度概要。厚生労働省
- 業界比較サイト(弁護士・労組運営の違いを整理した解説)。退職代行「ローキ(労働基準調査