「労働組合は会社に紐づいているものではないのか?」と疑問に思う方は多いです。とくに退職代行サービスの利用にあたり、労働組合がどのように関わるのか、企業内組合(会社に紐づく組合)と企業外労働組合(合同労組や一般労組)がどこで違うのかは重要なポイントです。
本記事では、わかりやすく段階を追って説明します。
労働組合の種類|企業内組合と企業外組合の違いを整理

労働組合には大きく分けて次のような形態があります。
企業内労働組合
特定の会社に所属する従業員が組織する労働組合で、会社に「紐づいている」組合です。例として自動車メーカーや大手通信会社の社内組合が挙げられます。
主な目的は、当該会社の従業員の労働条件改善や権利保護であり、会社と直接交渉して賃金や労働環境を話し合います。退職代行サービスとは通常無関係で、企業内組合が退職代行を行うことはほとんどありません。
企業外労働組合(合同労組・一般労組)
特定の会社に紐づかない組合で、個人や複数企業の労働者が加入できます。例として地域ユニオンや合同労働組合が該当します。個人加入が可能なため、特定の企業に所属していなくても参加できる点が特徴です。
退職代行サービスを提供する労働組合は、ほとんどがこの企業外組合の形態です。退職代行では、利用者が一時的にこの組合に加入(手続き上)し、組合が代理人として退職交渉を行います。
退職代行と労働組合の仕組み|企業外組合が選ばれる理由

退職代行で使われる労働組合は、ほとんどが企業外労働組合(合同労組)です。以下にその仕組みと特徴を整理します。
なぜ企業外労働組合が退職代行に使われるのか
企業外組合が退職代行に適している主な理由は次の通りです。
退職代行での違い:企業内組合と企業外組合を比較

例として、退職代行ローキは労働組合として登録され、利用者が一時加入することで合法的に有給消化や退職日調整の交渉を行う仕組みです(2025年の公表情報参照)。
注意点:信頼性と交渉の限界
労働組合の信頼性
労働組合を名乗るサービスの中には、登録が不十分だったり、実体が薄い「名ばかりの組合」が存在する可能性があります。利用前には厚生労働省の組合登録情報や、組合の実績(交渉件数、成果)を確認することが推奨されます。
交渉の限界
労働組合は団体交渉権に基づき退職条件の交渉を行えますが、訴訟代理権は持ちません。未払い賃金の訴訟や慰謝料請求など法的紛争が生じる場合は、弁護士による対応が必要です。労働組合運営のサービスは、紛争を避けるあるいは初期段階で解決することを得意としています。
企業外組合による退職代行が認められる法的根拠
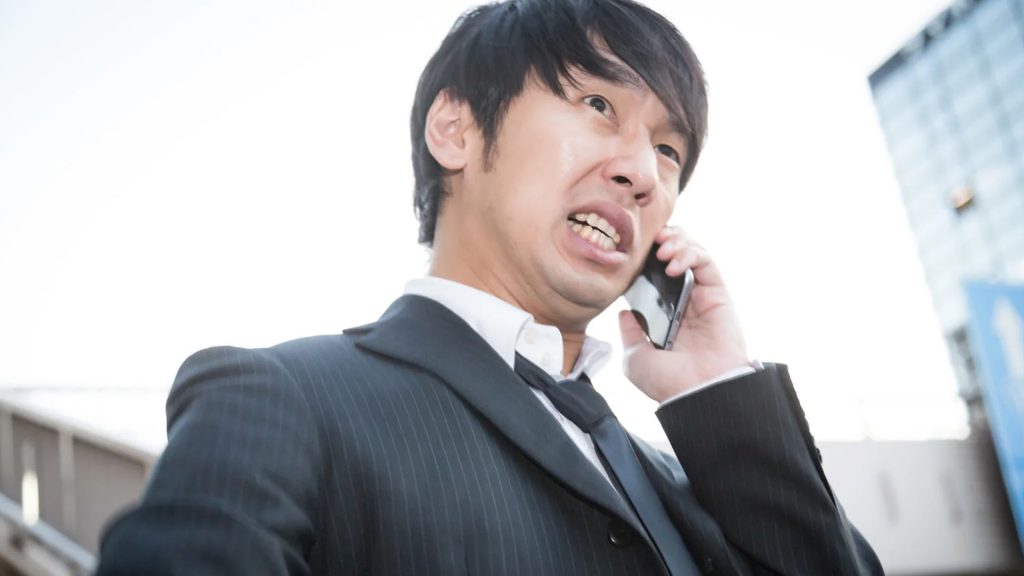
企業外労働組合が退職代行で交渉することが認められる理由は、労働組合法や憲法上の権利に基づくものです。
こうした点により、企業は単に「部外者だから拒否する」といった理由では団体交渉を拒めない仕組みになっています。
社外秘や個人情報保護の観点からの対応
社外秘の扱い
退職代行の交渉は通常、退職日や有給取得など労働条件に関する内容に限定されます。営業機密や技術情報といった企業秘密に踏み込むことは基本的にありません。そのため「社外秘」を理由に交渉を拒否するのは困難です。
個人情報保護の観点
退職代行では、利用者本人が組合に氏名や勤務先、退職意向等の情報を提供し、組合が代理人として動きます。これは本人の同意に基づく情報提供であり、個人情報保護法に抵触しません。信頼できる組合やサービスは、情報保護方針を明示し適切に管理しています。
企業側が個人情報保護を理由に拒否する場合は、組合が本人の委任状や確認書を提示して代理権を明確に示すことで、実務的に解決するケースが多いです。
企業内組合と企業外組合の特徴比較

企業側の実際の反応と現場の課題
まとめ|退職代行で企業外組合が選ばれる理由と注意点
退職代行サービスで広く使われているのは企業外労働組合(合同労組)です。利用者が一時的に組合に加入して団体交渉権を行使し、退職交渉を代理で進める仕組みになっています。この仕組みが認められる理由は、労働組合法に基づく団体交渉権が企業内・企業外を問わず適用されること、そして労働者がどの組合に加入するかは自由であることにあります。
企業が「部外者」「社外秘」「個人情報保護」を理由に交渉を拒否することは難しく、拒否すれば不当労働行為のリスクが生じます。個人情報は本人の同意を前提に適切に管理されるため、通常は問題になりません。ただし、組合の実体(登録状況や運用の透明性)や、交渉の限界(裁判等は弁護士が必要)については事前に確認することが重要です。
2025年時点では、企業外組合を使った退職代行が低コストかつ交渉力のバランスで支持されており、実際の利用が広がっています。



















