退職代行は「辞めたいけれど言えない人」の選択肢として広まっています。利用者にとって救いとなる側面がある一方で、「弱者を食い物にするビジネス(弱者ビジネス)」という批判も根強くあります。
なぜそう呼ばれるのか、問題点を順に整理し、最後に弁護士運営の退職代行を推奨する具体的理由とチェックリストを提示します。
なぜ「弱者ビジネス」と言われるのか|「脆弱な需要」と「情報の非対称」

退職代行が弱者ビジネスと評される最大の理由は、「追い詰められた労働者(情報・交渉力の弱い当事者)」の切実なニーズに事業者側が金銭を取って応じる構図にあります。
退職の手続き自体は本人が行えば済む場合でも、精神的に追い詰められている人は自分だけでは進められないことが多く、そこに数万円〜数十万円が課金されます。こうした需給の脆弱さにつけ込む業者が存在することが、まず批判の背景です。
典型的な問題点(1) ― 業務範囲と誇大広告
多くの民間業者は「即日退職」「成功率100%」といったキャッチコピーで集客しますが、実際のサービスは「退職の意思を会社に伝える」程度にとどまるケースが多く、未払い賃金請求や交渉はできない旨が小文字で書かれていることがあります。利用者側が十分に理解できないまま契約してしまうと、期待と現実のギャップが生じ、損失感が強まります。
典型的な問題点(2) ― 非弁行為・違法リスク
弁護士資格がない業者が「未払い賃金の請求」や「和解交渉」を行うと、弁護士法違反(非弁行為)に当たる可能性があります。弁護士会や法律専門家が繰り返し注意を促しており、非弁の線を越えれば業者だけでなく利用者も手続き面で面倒に巻き込まれることがあります。法律的な争点がある場合、弁護士以外の交渉はそもそも法的効力を持たないこともあるため注意が必要です。
典型的な問題点(3) ― 不透明な費用とエスカレーションの欠如
低価格を謳う業者の中には基本料金は安く提示しておき、実際に交渉が必要になった段階で「追加費用」を請求する例が報告されています。加えて、業者が自社だけで解決できない事態に陥った際のエスカレーション先(弁護士へ委ねる等)が用意されていないと、利用者が負うリスクが大きくなります。
社会的批判の背景 ─ 本当に「悪」か? 構造的要因の存在

一方で、退職代行を単純に非難するだけでは見えない側面もあります。深刻なパワハラや長時間労働で追い詰められた人が「声を上げられない」現実があり、その受け皿として市場が生まれた側面があることも指摘されています。
つまり、退職代行の流行は「サービスの良し悪し」だけでなく、職場の劣悪さや相談窓口の不足といった社会的な課題を反映している点は忘れてはいけません。
「弁護士監修」は安心ではない ─ 監修と運営は別物
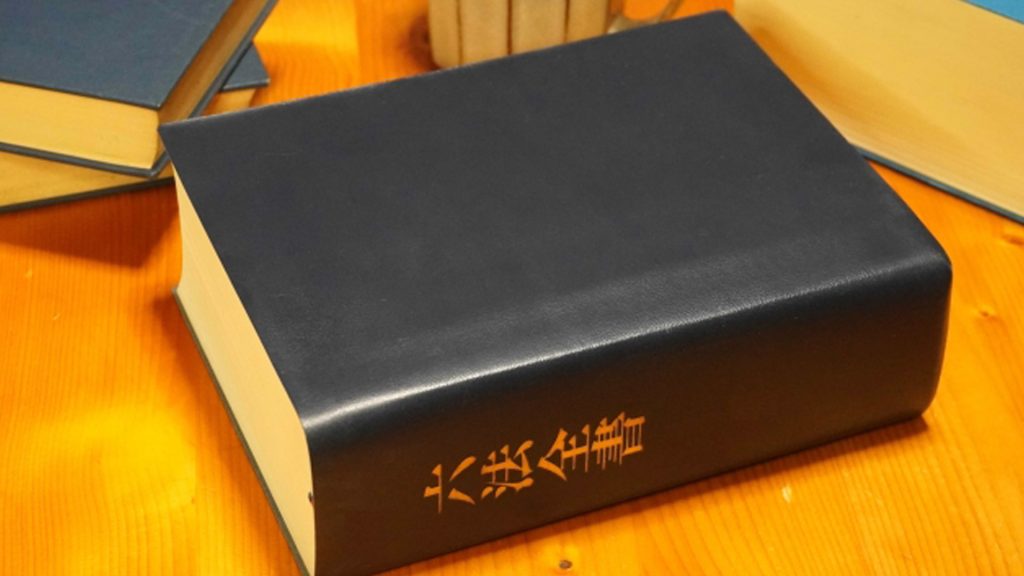
業者が「弁護士監修」を謳うケースが増えていますが、監修=弁護士が実際に交渉・代理しているとは限りません。監修は多くの場合「書面のリーガルチェック」や「運営方針の助言」に留まり、個別事件で弁護士が直接対応するわけではない点が問題です。
非弁リスクや交渉が必要になった場合、監修だけでは利用者の法的リスクを十分にカバーできません。したがって、本当に法的支援が必要な場面では「弁護士が直接対応する(弁護士運営)」サービスを選ぶべきです。
では、利用するならどう選ぶか ─ 弁護士運営の退職代行を推奨する理由
- 法的代理権がある:弁護士は未払い賃金や慰謝料など法的請求について正式に代理交渉・訴訟を行えます。これは民間事業者にない決定的な差です。
- 非弁リスクがない:弁護士が対応する限り、弁護士法違反の心配が不要です。交渉で法的問題が表面化してもそのまま弁護士が処理できます。
- 透明な費用構造と説明責任:専門家として費用・対応範囲を明示する義務があり、後から不当な追加請求を受けるリスクが下がります。
弁護士運営を選ぶ際の実務チェックリスト
それでも「民間」を選ぶ場合の最低限の注意点
民間業者を選ぶ場合は、(1)「退職の意思伝達のみ」を明示しているか、(2)追加費用・労働組合斡旋の有無と流れ、(3)過去の苦情や行政処分歴がないかを必ず確認します。民間が効果的に機能するのは、法的争点が発生しない単純事案に限られます。
まとめ ─ 弱者を守るための最小限のルール
退職代行は「辞めにくい人」のためのサービスとしての意義を持ちますが、弱者ビジネス化するリスクも現実にあります。サービスを利用するなら、まず「法的安全性」と「透明性」を最優先にしてください。
法的問題が絡む可能性が少しでもあるなら、弁護士が直接対応する退職代行(弁護士運営)を選ぶことが最も確実で安全な選択です。民間業者の「弁護士監修」は便利な表示ですが、実務上の代理権は与えません。あなたの権利を守るため、正しい窓口を使ってください。
弱者ビジネスの定義
社会的・経済的に立場が弱い人(情報・交渉力・資源が不足している層)の切実なニーズや困りごとを利用して、不当に高い利益を得たり、適切な説明や救済を伴わない形で商品・サービスを提供するビジネスのことです。
見分けるポイント
なぜ問題か
対象が弱い立場にあるため被害が発生しやすく、救済が難しい点です。社会的に不当な搾取につながるリスクがあります。
対処のヒント
出典・参考資料
- 東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」解説記事。(とべん)
- 朝日新聞「退職代行と弁護士会の注意喚起」報道。(朝日新聞)
- Diamond Online「退職代行に対する議論と批判」記事。(ダイヤモンド・オンライン)
- note 等の匿名体験/批判記事(弱者搾取の指摘)。(note(ノート))
- 労働基準調査組合や法務系解説(弁護士監修と弁護士運営の違い説明)。(退職代行「ローキ(労働基準調査組合)」)




















