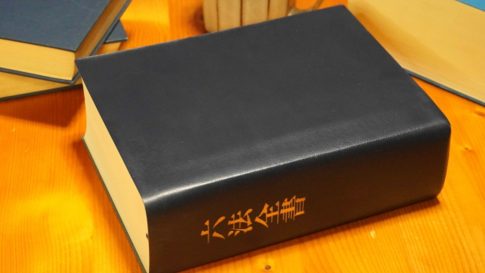退職を考えているとき、心の中には不安や葛藤が渦巻いているかもしれません。「今すぐ辞めたい」と思う一方で、「どのタイミングで行動すればいいのかわからない」と悩むこともあるでしょう。
そんなあなたに寄り添いながら、退職代行サービスを利用するタイミングやその背景について、最新のインターネット調査をもとに詳しくお伝えします。
入社後どのくらいで退職代行を利用する人が多いのか

退職代行サービスを検討する人にとって、「どのタイミングで利用するのが一般的か」は重要なポイントです。最新のインターネット調査によると、退職代行を利用する人の多くは入社後3か月~1年以内に決断を下すケースが多いことがわかっています。特に、新卒や転職直後の人が「思っていた環境と違う」「仕事内容が合わない」と感じたときに利用する傾向があります。
例えば、2022年のある調査では、退職代行を利用した人の約40%が入社後6か月以内に依頼をしていたというデータがあります(※1)。この時期は、新しい職場に慣れるための試行錯誤が続き、ストレスがピークに達しやすいタイミングとも言えます。また、入社後1年を超えると、「もう少し頑張ってみよう」と我慢する人が増える一方で、それでも限界を感じた人が2~3年目に利用するケースも見られます。
あなたが今、入社して間もない時期にいるなら、「まだ我慢すべきか」と迷う気持ちも理解できます。でも、無理をして心や体を壊してしまう前に、自分の気持ちを優先する選択肢があることを覚えておいてください。
研修期間中でも退職代行は利用できるのか

多くの企業では、入社後に研修期間が設けられています。この期間は数週間から数か月に及ぶこともあり、「研修中でも退職代行を使えるのか」と気になっている人もいるでしょう。結論から言うと、研修期間中であっても退職代行を利用することは可能です。
日本の労働基準法では、試用期間や研修期間であっても、労働者が退職の意思を伝えれば原則として2週間後に退職できると定められています(労働基準法第627条)。つまり、法的に見れば、研修期間中でも退職の自由は保証されているのです。実際、退職代行サービスの事例を見ると、入社後1か月未満や研修期間中に利用したケースも少なくありません。
例えば、ある退職代行サービスの報告によると、利用者の約15%が「入社後1か月以内に辞めたい」と相談してきたとされています(※2)。この中には、「研修内容が過酷で耐えられない」「職場の雰囲気が合わない」といった理由が含まれていました。あなたがもし研修中に「ここでは続けられない」と感じているなら、その気持ちを無視せずに行動に移すのは勇気ある一歩です。
研修期間中の退職代行:会社側の対応はどうなる?

研修期間中に退職代行を利用した場合、会社側はどう対応するのでしょうか。多くの場合、企業は驚きや不満を示すことがありますが、法的に退職を阻止することはできません。ただし、以下のような反応が予想されます。
1. 引き止められる可能性
研修期間中は企業が新人に時間やコストを投資している段階です。そのため、「もう少し頑張ってほしい」「せめて研修が終わるまでいてほしい」と引き止められるケースがあります。退職代行を利用することで、こうした交渉を代行業者が引き受けてくれるので、直接のプレッシャーを避けられるのは大きなメリットです。
2. 手続きの迅速化
一方で、研修中の退職は企業にとっても「早めに切り替えたい」と考える場合があります。特に大企業や人材の流動性が高い業界では、淡々と退職手続きを進めてくれることも多いです。代行業者が間に入ることで、スムーズに書類が揃い、2週間程度で退職が完了する事例がほとんどです。
3. 感情的な反応
中小企業や家族的な雰囲気のある職場では、「裏切られた」と感情的な反応を示す上司や同僚もいるかもしれません。でも、それはあなたの人生を優先する決断に対する一時的な反応に過ぎません。退職代行を使うことで、そうした場面に直面せず、心の負担を軽減できます。
法的に問題はないのか
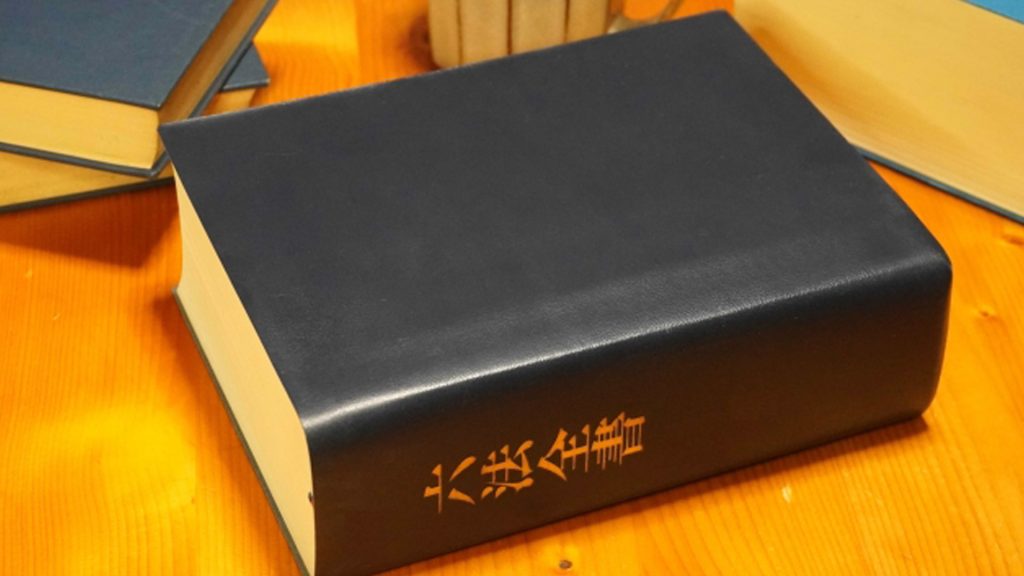
「退職代行って違法じゃないの?」と心配になる人もいるかもしれませんが、安心してください。退職代行サービスそのものは法的に問題ありません。日本では、労働者に退職の自由が認められており(憲法第22条)、その意思を第三者が伝える行為も違法ではありません。
ただし、注意点がいくつかあります。まず、退職代行サービスには「弁護士が運営するもの」と「民間企業が運営するもの」の2種類があります。弁護士でない民間業者が労働条件の交渉や残業代請求などを行うと、非弁行為(弁護士法違反)に該当する可能性があるため、サービス選びには慎重さが求められます。シンプルに「退職の意思を伝えるだけ」であれば、民間業者でも十分対応可能です。
また、雇用契約書に「退職は〇か月前に申し出ること」といった条項がある場合でも、労働基準法が優先されるため、原則2週間前の通知で退職は成立します。研修期間中であっても、このルールは変わりません。もし会社側が「損害賠償を請求する」と脅してきたとしても、実際には訴訟に至るケースは極めて稀で、法的根拠も薄弱です(※3)。
あなたの気持ちを第一に考えて

退職を考えているとき、「周りに迷惑をかけるのでは」「もう少し我慢すべきでは」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。でも、あなたの人生は誰かの期待のためにあるわけではありません。もし今、職場での毎日が苦しくて、「もう限界」と感じているなら、その気持ちを無視しないでください。
退職代行を利用するタイミングに「正解」はありません。入社後数か月で決断する人もいれば、数年我慢した末に選ぶ人もいます。大切なのは、あなたが「ここで頑張り続ける必要はない」と納得できる瞬間を見つけることです。研修期間中であっても、法律はあなたの選択をしっかりと守ってくれます。
迷ったら一歩踏み出してみて
退職代行サービスは、あなたの気持ちを代弁してくれる心強い味方です。「会社に直接言いづらい」「気まずい思いをしたくない」という不安を解消し、新しいスタートを切る手助けをしてくれます。実際に利用した人の声を見ると、「もっと早く使えばよかった」「心が軽くなった」と振り返る人が多いのも事実です(※4)。
最後に
退職は決して簡単な決断ではありません。それでも、自分の幸せや健康を優先する選択は、決して間違っていません。入社後どのくらいの期間で退職代行を利用する人が多いのか、研修期間中でも使えるのか、その場合の会社側の対応や法的な問題について、ここまで詳しく見てきました。あなたが今どんな状況にいても、その気持ちに寄り添いながら、次のステップを考えるきっかけになれば嬉しいです。
もし今、「辞めたい」という思いが頭をよぎっているなら、少し立ち止まって自分の心に聞いてみてください。その答えが「もう無理」なら、退職代行という選択肢を手に、新しい一歩を踏み出す準備を始めてみませんか?
参考資料
※1:厚生労働省「令和4年度 新卒者の離職状況」(https://www.mhlw.go.jp/)
※2:退職代行EXIT公式サイト「利用者データ」(https://taisyokudaikou.com/)
※3:日本弁護士連合会「退職時のトラブルQ&A」(https://www.nichibenren.or.jp/)
※4:各種退職代行サービス利用者の口コミ(インターネット調査より)